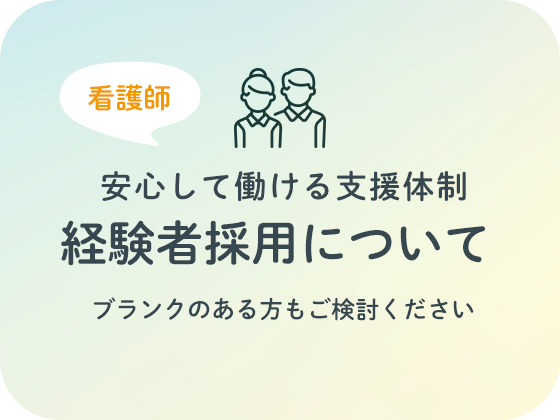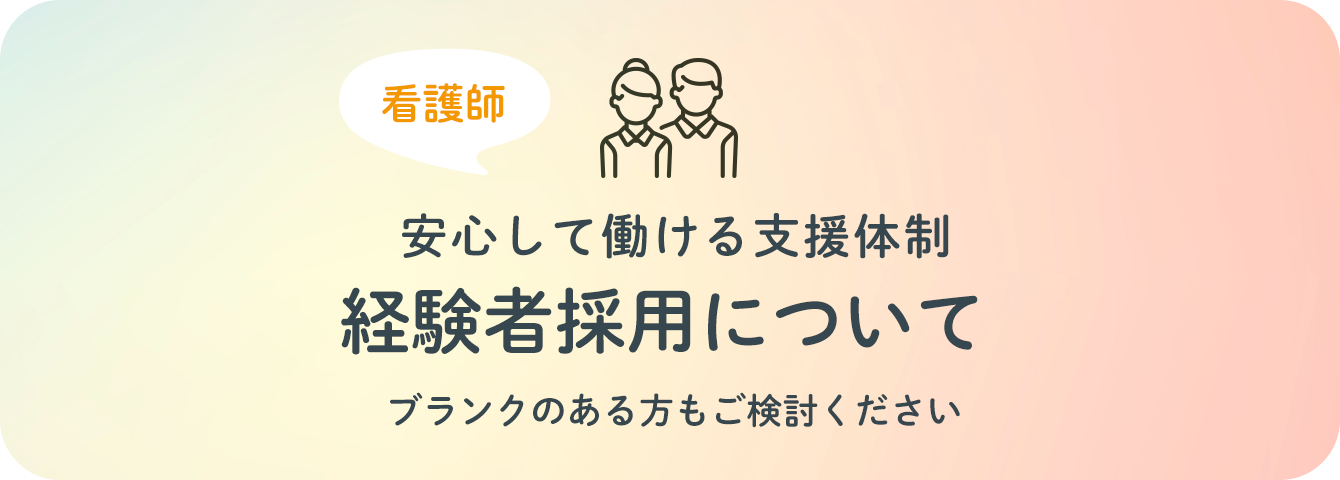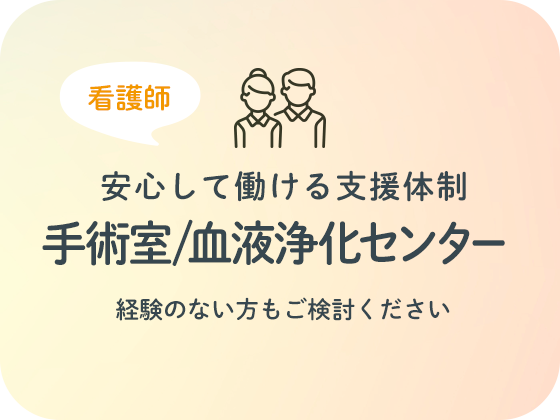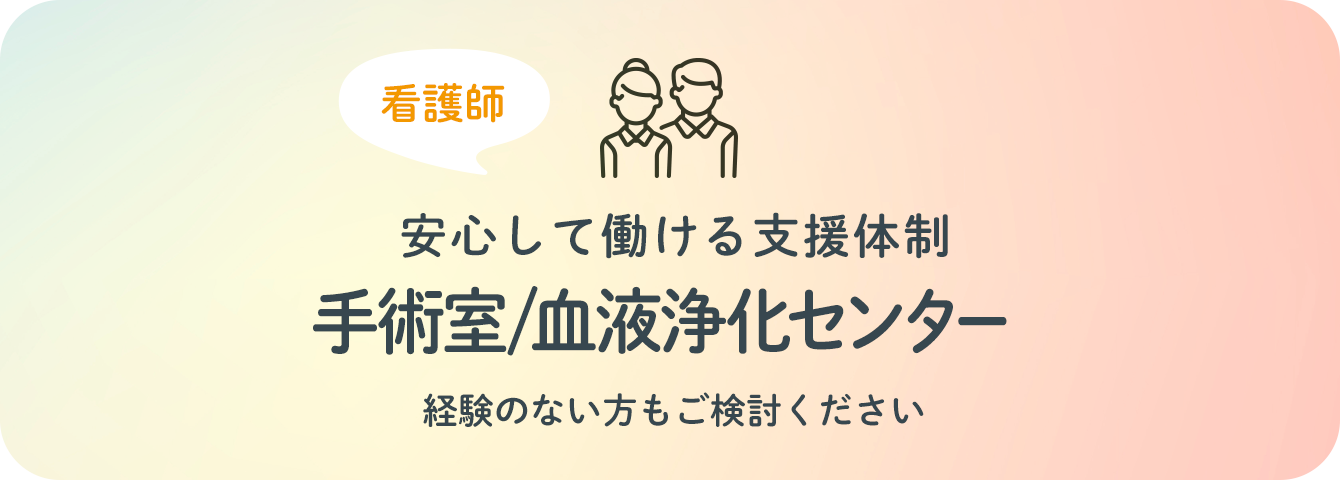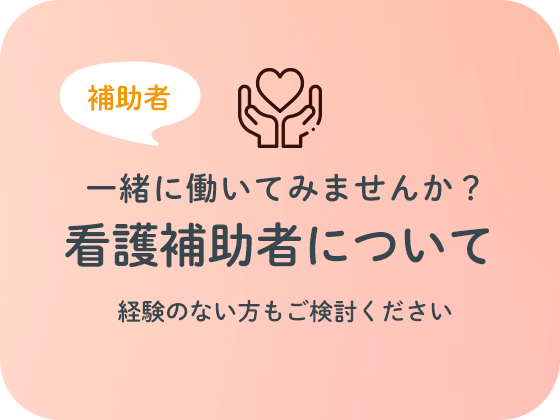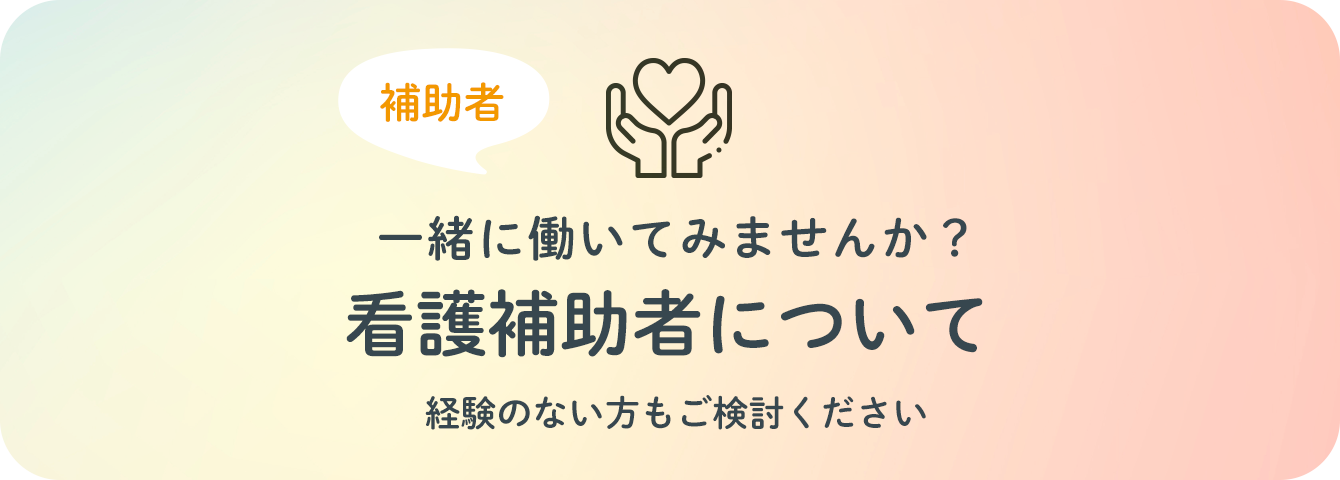新人研修を通して様々な経験をし、自分が大切にしたい看護を見つけることができます。
メッセージ
働く人たち
急性期から回復期、慢性期までさまざまな医療を提供する三島南病院では、それぞれの目標やライフスタイルに合わせた看護を経験し、専門性を深め、成長していくことができます。
皆さんの未来の姿を想像しながら、先輩たちの看護への熱い想いを感じてください。
未来の後輩へのエール!


大学病院での研修機会が多く、個人の成長が実感できる病院です。チームとしてともに学びつづけましょう。

色々なことを乗り越えることで、看護はいつしかやりがいへと変化する素晴らしい仕事です。チームみんなであなたの成長を支えます。

院内・院外研修が豊富。通常業務だけでなく、個人の成長にも力を入れています!
既卒者採用/看護補助者への応募を検討されている方へ
入職してからの教育・サポート体制やお仕事内容について
以下のページで詳しくご案内します